■
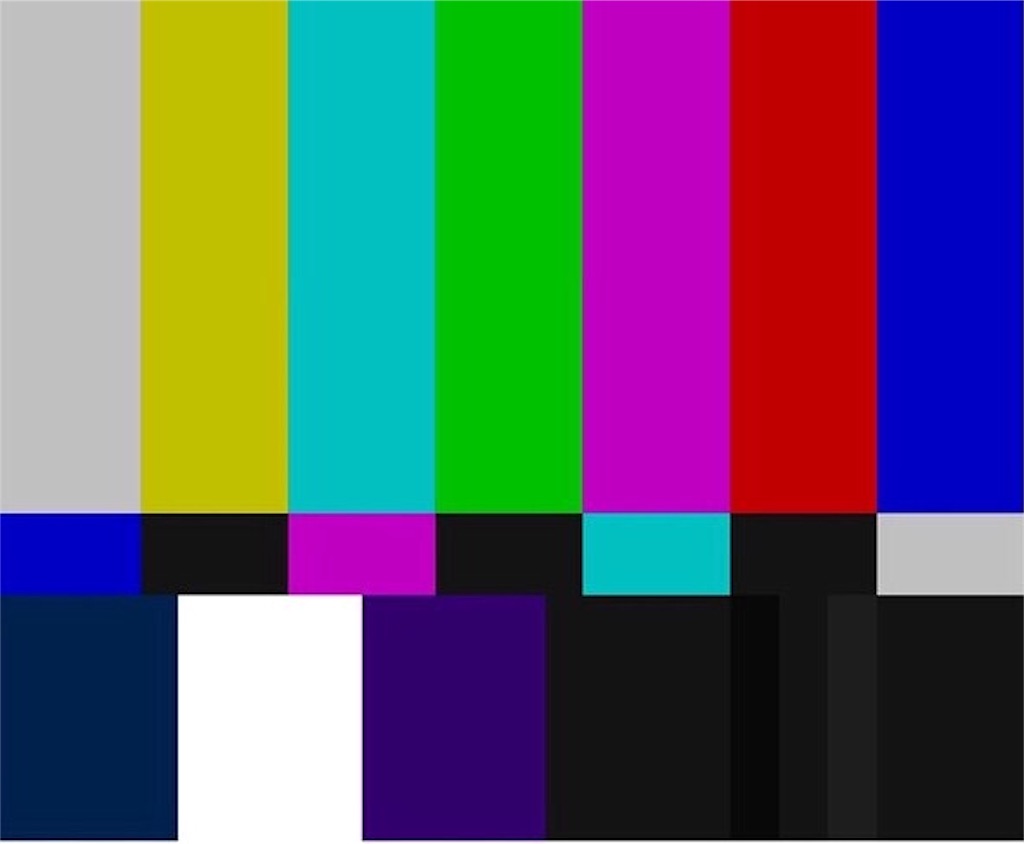
暗闇にぼうっとひかる桜の樹の下のハイヒールで歩く腐葉土に屍体はいないと思う。死者が行くところなんてありません、宇宙的には。
わたしたちは星を見ながらよく話す。月明かりに照らされながら砂漠のはなしをして、こちらとあちらの彼岸に道路の白線を辿る。まっすぐ歩けない。きちんと立てているか自信がない。気象衛星の視線に後ろめたくなる。あらゆる文字として大事な言葉を思い出しながら、ぼたぼた落ちる声は不随意だった。たよりがないのはつめたい肉体ばかりのこのからだで熱を持つたび遠ざかる影の立体交差する曖昧な曲線、わたしたちの似ている位相のちかく、ある座標にギラっと星が流れて、わたしの速度がその時空へ追いついたときのことを思った。フィラメントのあいだを音もない飛行機がすり抜ける。もらった煙草はすんなり肺に馴染んだ。
夜に会うたびに正確な落雷を待っている。家を通り過ぎて、ここはすごく寒い、街の灯りをひとつひとつ、そこにある幾千の生活、降り注ぐ名前のことを思い、なつかしい夜の半径を歩いた。夢のなかで空からこの光景を見たことがある。ような気がする。わたしのなかは空洞で、わたしは常に誰かの漸近線であると思う。街を遮れば星は見えるのにそうしなかった。ポケットのなかでも夜は手に入らなくて詩集はいつまでたっても見つからない。喉を猫でいっぱいにする。周波数を乱すのは暗くてやさしい音楽だけでいい。