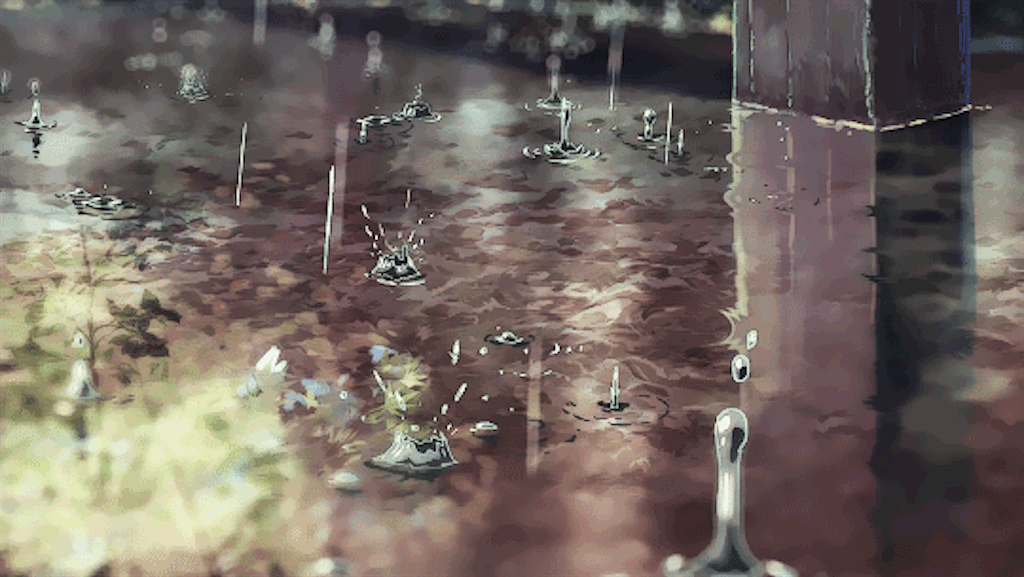因果律

日曜の昼までたっぷり惰眠を貪って、社会人から退化するために学生気分の変な服を着て外に出る。塞がりかけたピアスをブチ抜いて、それでも鞄の中に入っているのは日本経済新聞で、あんなに最悪な思想だと思ってた結婚のことばかり考えて、自分がどんどんしっちゃかめっちゃかになっていく。
プロントで広げた便箋の上に勝手にぼたぼた落ちていくのに、どれだけ足しても足りない言葉に嫌気がさして、ほんとは言わなくてもいいことばかり書いてしまう。よしんば愛し合っても1度、その1度がこの手紙のように長ったらしいとは限らず、それでも勝手に信頼したから放った告白がある。人は結局わかりあえないので、すこしでも知ってもらうための祈りのような手紙をしたためる。草々。さいごに付け加えた今日の日付を見てもやもやしていた気持ちに理由をつけた。290円で買った時間。そのあいだに黙々と灰になる420円。衰えていく自分の身体と、青空文庫で読む0円の『桜桃』のどちらに価値があるんだろう。そんなの自明のことですね。なにも悪いことはしていないのにスーツ姿の人間とすれ違うたびに頭を振って前髪を目にかける。
週末になるといつもわからなくなってしまう。どうやって生きていればいいのか。これから死ぬまで生きることがまだ信じられない。インターネットに接続されている世界と、月曜日の朝から生きる世界と、どう折り合いをつければいいんだろう。そういうのがわからなくてバカだからせっかくの休日に人に会いたいわけがないのに化粧をして外へ出てしまうし。行かないのに映画館の上映スケジュールを眺めて2時10分からのズートピアに間に合わないことを確認してしまうし。やることもないのに帰りたくなくて生温い駅の裏のよくわからない段差に座り込んでしまうし。定期的な溜息に寄り添うみたいにピン、ポーン、と流れ続ける盲導鈴。あーあ、都心の駅のことを思って目を閉じる。雨や音楽や匂いがいろんな思い出の接続点となって虚像の感情が立ち現れる。帰れば生家は壊されるというニュースを食卓で聞き、どんどん居場所がなくなっていく。わたしの夏が奪われる。
明日の弁当をつくりながら、大人ってすごいなーと言ってみる。仕事に行きたくないときどうしてるって訊いたらパパは惰性で行くって言ってた。まだ22歳かーとこぼしたらママはまた週末のアレが始まったって言って笑った。たまらなくなったらテレビのほうを向いて録画してたアニメをつける。月曜への私情を混同して泣くなんてアニメにたいする冒涜だと思う。ごめんなさい。すみませんでした。わたしだってつよくなりたい。離れた世界で繰り広げられる暑苦しい友情はこんなにも甘美で、ひねくれることなく自分の感情を受け入れられるのはフィクションの中だけです。フィクションのなかのヒーローはまっとうに輝いて、他人のことを眩しいとか思ったりしない。現実世界にヒーローはいない。いてたまるか。というか、ヒーローが現れるような非常事態なんて身近に起こりはしない。仕事中に鳴った地震速報に、いろんな意味で胸が疼いてごめんなさい。このつまらん今が人生の本番であることを無視し続けてごめんなさい。盲目に信じないと意味がない。考えたって意味がない。懺悔しても意味がないのに、この苦しさはなんだろうか。
いのちの名前

谷底

こわいおもい
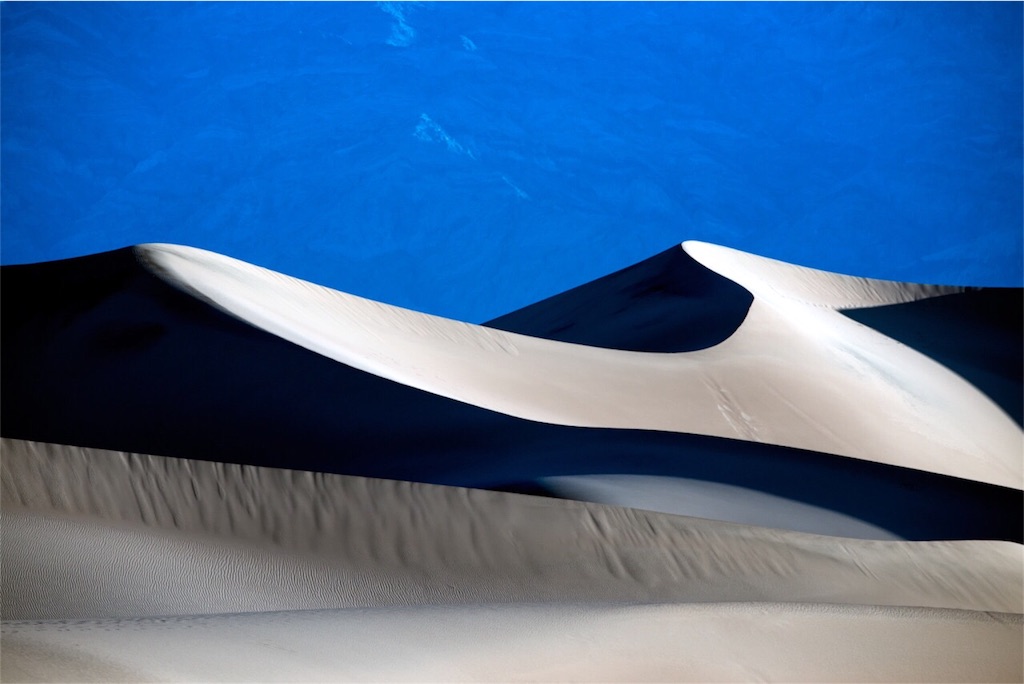
400回の未遂

告白

なにもかも通り過ぎて使い果てて動かなくなった 想像して想像して想像して想像して行動に移さない わたしはぜんぜんがんばれないから
ここ数年は好意に応えることをぱったりやめてしまっていたので、わたしはありがとうって言った、そしたらはっきり伝えてくれて、だけどかたちだけ曖昧なまましてくれて優しかった わたしがきちんと明確に鮮やかに境界を跨いでしまったときの心圧を鑑みればほんとうに落ち込んでしまってダメになってしまう
たぶん奥のほうではまだ男のひとがこわい 生温かい夏の予感みたいな風なのに内臓がぶるぶる震えていて、はじめてからだをひらいたときに似ていると思った 覆い被さる夜闇はひどくやさしくて、柔らかなわたしを迫害する せんせい、とわたしの口が言い、どんどん自分が遠くへ行くような感じがした こわくて、みじめで、ぜんぜん大丈夫になれなくて、きもちだけがつよくて毅然としてて平気でまともで、肉体が付いてきてくれない いつもそう ハタチになったときみたいなきもち 圧倒的っぽい境界を跨いだのに毎日や自分自身はなんにも変わらない わたしはバカだと思う ほんとうにバカすぎて呆れる 恋情に断絶がないほど相対的に断絶がうまれるということ じぶん何言ってるかわかんねーなまじ
雨の中の庭