形而上学的・夜

夜の公園でブランコを揺すりながら、遠くにバスを何本も見送って、帰りそびれた鞄のなかで無塩バターが溶けていく。適当なお酒を買い、適当に煙草をのんで、適当にブランコを漕ぐ。夜に放り投げるイメージ。汚れた靴、ときどき星が見える。地面と空を行き来するあいだ、からだがドレッシングの油を混ぜるみたいになって眩暈が全身に回っていく。止められなくてハイヒールの底が減る。
キリンジを歌いながらiPhoneを眺めていたら、ある文章がつめたいということが書かれており、その文章はわたしにとっては暑い、真夏が死んで冷める前の生暖かい夜風、渇いた路地に腐敗する果物の匂い、蒸せかえるようなそのなかに取り残された猥雑な暗がりみたいなものだけど、淡々冷淡、そのことを思えばつめたいとは言えるものの、あー、この人の体温は高いんだなー、と思った。
大人になってから、ずっとなにかを待っている。溜息みたいなことばを落としながらそのあとの世界のことを想像する。だからいとも簡単に物語に食われてしまう。わたくしは空洞なので、浸食するのはいとも容易いだろうな。煙草の匂いの染み付いた指先を鬱陶しく思い、自分のことすら鬱陶しいのに他人なんてなー、みんなにはみんなの生活がある、それでもときどき交差しなくてはならない幸福な他人のこと、どうにかしてかなくちゃなんないよ、会えないこともある、だからいちばんに辿り着いてくれたら一等賞です。
代々木の夏にあなたって太陽の塔好きですよねーと言われて返答を言い淀んだとき脳に何言ってんだ好きだろお前好きだろという声が聞こえて、好きっていうかー、いや好きです、みたいな歯切れのよくない反応しかできないのはわたしの恋が適当だからで、カテゴライズされることから逃走し続けているからで、いつまでも感覚に名前をあげないからぜんぶがふわふわしていてなんにも言えなくてほんとつまんないし、何回確かめても閾値は閾値なのでもうダメだ、ベロニカは恋的に死ぬことにした。
貝の火

■
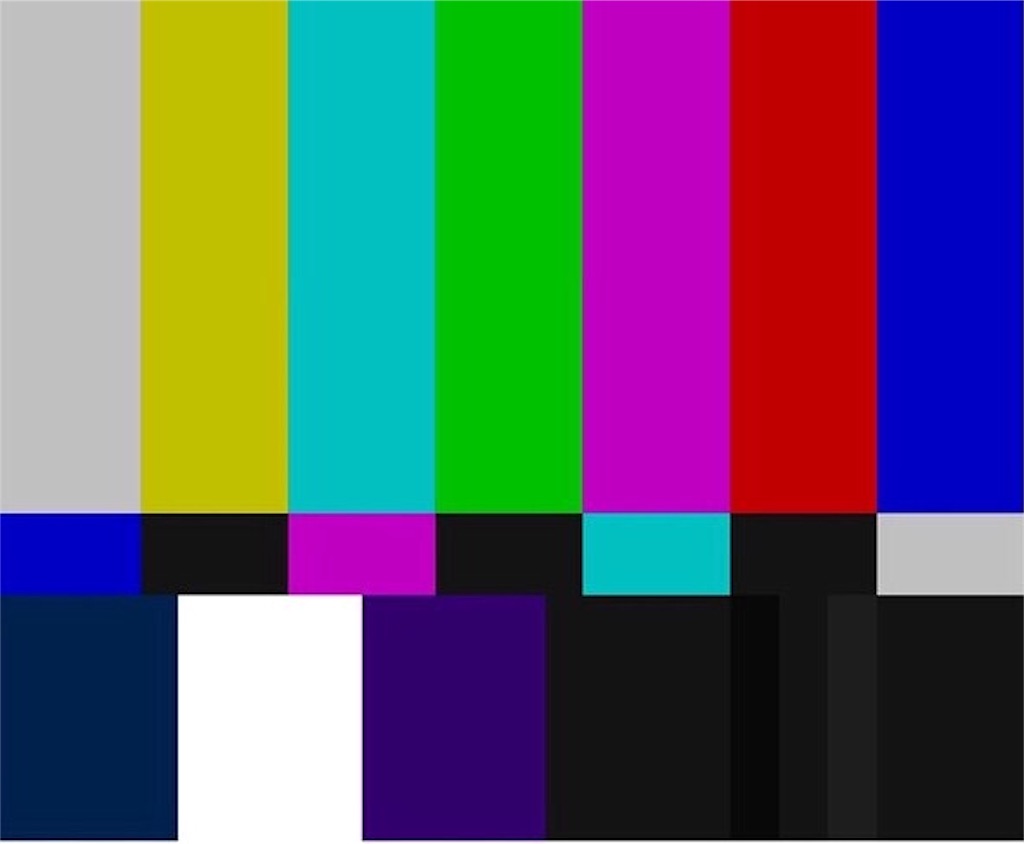
罠

演劇的な都市で心地よく生活するっていうこと

グラン・ギニョールの恋人

最適の日
